「自己脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた内臓脂肪症候群に起因する動脈硬化症治療』ご存知ですか?脂肪由来幹細胞による肌の再生医療。最近注目を浴びていますよね?
自己脂肪組織由来間葉系幹細胞を用いた治療について
脂肪組織由来間葉系幹細胞(以下ADSC)とは、脂肪組織に含まれる僅かな幹細胞を分離・培養して増やした(増殖させた)細胞のことを指します。このADSCはとても柔軟な能力を持っており、神経や血管ばかりでなく多様な臓器や組織を構築する細胞に分化する能力が確認されています。近年ではこのADSCが身体の様々な病態を調節し、正常化する機能を持つことが明らかになりつつあります。本治療は、ADSCを用いて内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)による主にアテローム性動脈硬化を予防もしくは治療し、患者さんの生活習慣病の改善を目的とします。
動脈硬化症は、本人に自覚がない疾患です。一般的に内臓脂肪症候群に伴う脂質異常症は、生活習慣病に関連することが知られており、総合的な治療が必要になります。
動脈硬化症は3種類に分けられますが、医療現場で最も問題となっている動脈硬化は、アテローム性動脈硬化です。主に脂質異常症に関連が深く、放置することで、虚血性心疾患(狭心症・急性心筋梗塞)、脳梗塞など死に至る病気のリスク因子になります。アテローム性動脈硬化の正確な発症メカニズムはわかっていませんが、血管内皮細胞が何らかの理由で損傷すると、その傷をきっかけとして脂質が沈着してしまいます。そして生活習慣病(糖尿病・高血圧症など)や生活習慣などがキッカケで、沈着した脂質は酸化脂質となってしまいます。こうなると、身体が病的状態と認識して様々な防御反応を引き起こし、最終的に防御に関わった細胞が死んで脂質沈着周囲に溜まっていきます。これがアテローム性動脈硬化の原理です。こうなると、血管が細くなってしまい血液の通りが悪くなるばかりか、血管自体が大変脆くなってしまいます。

本治療は、投与したADSCが、損傷した血管内皮細胞周囲に集積する性質を利用し損傷に伴う慢性的な炎症を抑制し組織修復を行うことを期待する治療です。重要なことは、投与したADSCが直接治療に関わるわけではなく、周囲の細胞に働きかけて患者さんの自己治癒力を引き出すことを目指した治療である、ということです。従って、これまでの治療は引き続き継続することが大変重要です。
本治療は、患者さんの脂肪組織の一部を採取して、清潔な環境でADSCという幹細胞を増やし、必要なタイミングでその細胞を静脈から点滴投与する治療です。採取する脂肪組織は5g程度で、この脂肪を原料にADSCを培養します。注入するADSCはご自身の細胞ですので感染症の危険性はありません。培養して増やした細胞の一部は、長期間冷凍保管して次の治療に使用することができます。
この治療は、再生医療等安全性確保法という法律に則り厚生労働省に認定された「特定認定再生医療等委員会」での審査を経て、厚生労働大臣に提出した書類に基づき実施しています。
※審査に関する問合せ先:医療法人社団優恵会特定認定再生医療等委員会
(認定番号:NA8200002,連絡先:03-5719-2306)
治療の方法と治療期間について
1. はじめに組織提供に関わる説明です。
この治療を実施するためには、患者さんご自身から脂肪組織を少量採取する必要があります。ADSCを培養するために、患者さんの脂肪組織をお腹などから5g程度採取します。採取時には局所麻酔を使用しますが、採取した部位が元の状態に回復するには2週間程度必要です。
2. 続いて、再生医療を受ける説明です。
得られた脂肪組織から幹細胞(ADSC)を取り出し、特殊な培養操作を行い、治療に必要な細胞数まで増殖させます。治療に必要な細胞数の培養が完了するまで約2ヶ月間程度が必要です。
3. 治療の方法の説明です。
患者さんから提供された脂肪組織を、細胞加工施設において培養し、完成した培養細胞(ADSC)を点滴用注射液に充填します。これをADSC細胞加工物と呼びます。投与する患者さんのADSCは、細胞を作る過程で感染していないこと、生存率が適正であること、幹細胞の機能を維持していることを事前に確認しています。点滴用注射液に充填したADSCは、クリニックで1時間から1時間30分程度の時間をかけて静脈から点滴注射します。投与後は、最大1時間程度(平均15~30分)院内で安静にし、その後ご帰宅いただきます。
治療後は、効果の有無や異常等がないことを確認するために6ヶ月間は定期的に通院していただきます(概ね月1回)。
治療に用いなかったADSCは、ご希望により、細胞を培養した施設で安全に冷凍保管され、将来、必要な時に再び治療に用いることができます(別途契約が必要)。
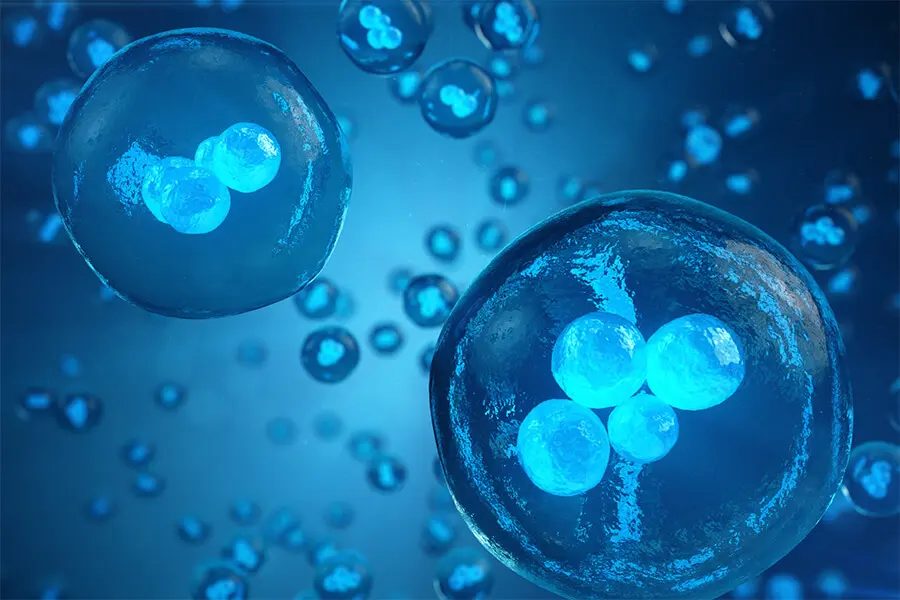
<治療を受けられない場合(除外基準)>
患者さんの皮膚を切開し、脂肪組織を採取します。使用する局所麻酔に過敏症の方は、脂肪を採取できないため治療を受けることができません。病気を治療するためにお薬を服用している場合は、そのお薬の作用で本来の効果が得られない可能性があり、場合によっては悪化する可能性もあります。服用しているお薬の種類によっては治療をうけることができない場合があります。
治療を受ける前に主治医と相談してください。また、この治療法は「バイ菌」を殺すような消毒薬のような働きはありませんので、治療する目的の部位が感染していたりすると治療を受けることができません。
選択基準
1. 18歳以上の者
2. 内臓脂肪症候群に伴う動脈硬化症と診断された者
3. 標準治療法で満足な治療効果が認められなかった、あるいは用いられる薬の副作用等を懸念して標準治療を希望していない者
除外基準
再生医療等を受けようとする者が以下の基準に該当する場合には、本治療を行わない。
1. 脂肪組織の採取が困難な者
2. 悪性腫瘍に罹患中の者
3. 組織採取部位に感染を伴う、もしくは感染症に罹患中の者
4. 患者本人の意思で、同意書に署名出来ない者
5. その他、担当医師(実施医師)が不適当と判断した者
4. 治療が中止される場合について
以下のような場合この治療を中止することがあります。場合によっては、患者さんが治療を続けたいと思われても、治療を中止することがありますので、ご了承ください。
1. 患者さんが治療をやめたいとおっしゃった場合。
2. 検査などの結果、患者さんの症状が治療に合わないことがわかった場合。
3. 患者さんに副作用が現れ、治療を続けることが好ましくないと担当医師が判断した場合。
4. 標準的な細胞培養をおこなった結果、個人差等の理由により治療に必要な脂肪組織由来間葉系幹細胞が得られなかった場合。
その他にも担当医師の判断で必要と考えられた場合には、治療を中止することがあります。中止時には中止の理由を説明します。そして、安全性の確認のために検査を行います。また副作用により治療を中止した場合も、その副作用がなくなるまで検査や質問をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。

5. 予測される利益(効果)と不利益(副作用)について
(予測される利益(効果))
脂肪由来間葉系幹細胞が身体の組織・臓器の支配神経に働きかけて、動脈硬化症状を改善して、内臓脂肪症候群に伴うリスクファクターを軽減したり、生活習慣病を改善することで、日常生活・社会生活・活動性の向上が期待されます。ただし、治療の効果には個人差がありますので、あらかじめご了承ください。
(予測される不利益(副作用))
皮膚を切開し脂肪組織を採取する必要があります。採取の際には局所麻酔を用いますが、切開した部分は元に戻るまでに2週間程度必要となります。清潔に処置をしていますが、稀に組織採取部位が化膿するなどの危険が考えられます。
細胞を加工する際に、動物(ウシ・ブタ)由来の原材料を用いる工程があります。これらは調製過程で希釈され、成分はほとんど消失しますが、この原材料に対して稀に過敏症を引き起こす可能性は否定できません。
広く国内で実施されているADSCの点滴投与ですが、過去に投与後に肺塞栓で死亡した症例が国内で一例報告されています。この事故でADSC投与と死亡の因果関係が精査されましたが因果関係は特定されませんでした。
一方、厚生労働省と日本再生医療学会は、2023年7月14日に『間葉系幹細胞等の経静脈内投与の安全な実施への提言』を発言し、「実施に伴う危険性について、再生医療を受ける患者さんにしっかり説明すること」としております。この事はリスクの説明は勿論ですが、しっかり管理された細胞加工施設・医療機関において実施されれば問題がないことを意味しております。
当院が提携する細胞加工施設は、すでに多くの経験と実績を有しており、このようなリスクについても熟知した上で細胞加工を実施しております。また当院は万が一の場合にも対応できるよう、万全な体制が整っており、近隣の救急病院とも連携しています。治療後6ヶ月間は概ね月に一回程度来院いただき、治療効果と上記の有害事象がないことを確認する必要があります。組織採取部位や点滴治療後にいつもと違う症状などが現れたら、相談窓口までご連絡下さい。症状に応じた最善の処置を行います。
一般社団法人日本内分泌学会
http://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=58
一般社団法人日本動脈硬化学会
https://www.j-athero.org/jp/general/index/
などを参考にして、最新の治療法・予防法をご確認いただき、現在の患者さんの状態をご自身で把握した上で、専門家の意見も含めて本治療の必要性をご判断ください。

